今回は、ブログのタイトルにもついているギフテッドについてお話をしていきます。
ギフテッドの定義
最近、「ギフテッド」という言葉は日本でも聞かれるようになってきました。私が幼いころは、その言葉を聞くことはなく、天才・秀才などで表現されるもののそれは誉め言葉であると共に、奇人・変人・変わり者という言葉達と紙一重だったようにも思います。私も小学校に呼び出されたことがありましたが、「砂月君は、他の子たちと比べて、少し変わっている子のようでして・・・」と問題児のように言われたことを覚えています。
実は、この「ギフテッド」という言葉、国際的に共通している定義はなく国ごとに定められています。
アメリカ
アメリカはギフテッド教育の先進国とされ、ギフテッドの定義も比較的広範です。
連邦政府の定義は「知性、創造性、芸術性、リーダーシップ、または特定の学問分野で高い達成能力を持つため、その能力をフルに開発させるために通常の学校教育以上のサービスや活動を必要とする子どもたち」とされています。
日本で注目されるIQについてですが、一般的な目安としてIQ130以上が用いられることもありますが、あくまで一つの基準という位置づけであり、IQだけでは定義されません。
ギフテッド教育の専門家であるジョセフ・レンズーリ博士は、ギフテッドを以下の3つの要素が組み合わさったものと定義しています。(レンズ―リ博士の三環説と呼ばれます。)
ギフテッド向けの教育は多彩で、通常クラスに所属しながら専用の特別課題をこなすスタイル、特別クラスや特別学校に通うスタイル、飛び級システムなどがあり、知識の詰め込みだけでなく、好奇心や創造性を伸ばす教育方針がとられています。
イギリス
イギリスでは、「ギフテッド(Gifted)」と「タレンテッド(Talented)」を区別する場合があります。
以前は政府の補助金が出ていましたが、現在は財政的な理由からその制度はなくなっており、私立学校が積極的にギフテッド・タレンテッド教育を提供している傾向にあります。
フランス
フランスでは、他国に比べてギフテッドは主にIQによって定義される傾向が強いです。
IQの高い子どもは一般的に学校で優秀な成績を収めることが多いため、ギフテッド教育の重要性はアメリカなどに比べて低く見られていました。そのため、教育は私立校が中心となっています。
日本
日本には、実は公式な「ギフテッド」の定義はありません。
2021年に「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議」が立ち上げられ、特異な才能のある子どもたちへの支援のあり方が議論されています。
最近、ギフテッドという言葉が聞かれるようになりましたが、大半はクイズ番組。「IQ130越えのギフテッド」のような文言が紹介文に記載されているのをよく見かけます。
あとは「メンサ(MENSA)」についての記載が多いですね。全人口の上位2%にあたる高い知能指数(IQ)を持つ人々が参加できる、世界的な非営利団体ということでIQの高さを証明する一つのステータスになっているようです。私はMENSAについては詳しくないので、うまく説明はできませんが。
日本におけるギフテッドのイメージ
日本で自分はギフテッドだというと、訝しげな顔をされます。それには、日本の文化的背景があるのだと思います。
「ギフテッド=天才」という誤解
日本では、「ギフテッド」という言葉が、海外の教育現場で使われている意味合いよりも「何でもできる超人的な天才」という、非常に限定的で非現実的なイメージでとらえられているように思います。
例えば自己申告した人が、すべての学業成績が突出しているわけではない場合。特定の分野だけが異常に得意、もしくは異常に不得意など、イメージにそぐわない場合は、「本当にギフテッドなのか?」「ただの勘違いなのではないか?」と疑いの目を向けられることになります。
自己アピールに対する文化的抵抗
日本社会には「謙虚さ」を美徳とする文化が根強くあります。自分の能力や才能を声高に主張することは、協調性を欠いた「傲慢な態度」だと受け取られることが少なくありません。
「ギフテッドです」という言葉は、相手に「自分は他の人とは違う、特別な存在です」と主張しているように聞こえてしまい、心理的な距離感を生んでしまっていることが考えられます。
基準の曖昧さから来る疑念
ギフテッドは発達障害のように公的な判断基準があるわけではありません。そのため、自己判断であったり、民間の知能検査の結果だけで判断されたりする場合が多くあります。そのため、客観的な根拠が不明瞭だと見なされがちです。
その結果、「本当にそうなのか?」という疑問が生まれ、相手は懐疑的な態度をとってしまうことにつながっているように思います。
私は普通である必要があった
ギフテッドだなんて思っていなかった
日本では、ギフテッドだと自白することは、相手の無理解や固定概念にぶつかる可能性が他国よりも高いと思われます。それは文化的な背景から致し方ないことだとは思います。ギフテッド=スーパーカーだという例えが独り歩きして、ギフテッドが持つ多様な特性や、それに伴う困難がまだ十分に社会で共有されていないことにつながっているように思います。
私はIQだけで言うと140程度あります。受験の際の偏差値も70を超えていました。ただ、テストでどれだけのことが分かるのか疑問ですし、すべてのことが完璧にできるわけではありません。完璧主義者ではあるので、仕事では上司から「ミスターパーフェクト」とあだ名をつけられたり、「お前に任せておけば、多少の無茶ぶりは全部うまくいく」と言われることは多々ありました。
それでも私は自分がギフテッドだとは思うことなく、今まで生活してきました。私には苦手なことはありますし、知らないことも山ほどありますから。
ギフテッドだと一旦認めることにした
うつ病になり自分の人生を振り返る期間を持つことになりました。振り返る中で、様々な人の人生にも触れることになりました。そして、自称「ギフテッド」(ここで「自称」とつけるのは失礼なことなのかもしれません。ただ、定義がないので「自称」とつけさせていただいております。)の皆様に触れた時、私の人生と共通するものが数多くありました。
私は幼いころから、「普通」になるように育てられました。出る杭は打たれるから、出すぎないように。秀才であってもいいけど、冒険など危ない橋は渡らず。安定する公務員になって、一般的に幸せだと言われる家庭を持って。みんながすることをして、みんながしないことはしないように。
学校に呼び出された後も、「変わった子だと言われるから、みんなの真似をしなさい」と言われました。
なので、日常に感じる違和感は自分が間違っているのだと思っていました。自分が変えないといけない、変わらないといけないことだと。
授業が退屈だと思うことも間違い、大人としか話題が合わず同級生とは話が合わないことも間違い、使った言葉を理解してもらえないのも自分の言葉選びの間違い。曲がったことが大嫌いなのも間違い、ルールの矛盾や教科書の矛盾に気づいてしまうのも間違い。自分が感じたことを口にしても共感してもらえなければ間違い。
そうやって生きてきました。自分は特別ではない、ただ間違っているだけなんだとひたすら言い聞かせて。
でも、そうやって私がことごとく否定し続けてきたことと同じ体験をしている人達の話に出合うことができました。共通点がありすぎて、無視したり、気づかないふりをしたりすることすらできませんでした。
自分が隠し続けて、否定し続けて、気づかないふりをし続けて、自己否定し続けていた部分が間違いではなかったのだと、自然と涙があふれていました。
今でも、「ギフテッドですか?」と言われて「そうです。」とは言えません。ただ、そうなのかもしれないなとは思っています。
定義すらない、そんなあやふや分類に、そこまで大きな意味があるとも思えませんし。
私が考えるギフテッド
ギフテッドはよくスーパーカーに例えられるのを聞きます。私はそれとは違う感覚を持っています。
私は、ギフテッドは除雪車だと感じています。
普通車とは違うエンジンを積んで、特殊な機能もある。普通の車ではないことは間違いありません。ただ、その機能が生きるのは、特定の季節と地域だけ。一般道を走るには大きすぎるし、スピードなんてそんなに出ません。どちらかというと一般道を走るには向いていない車。ただ、季節や地域、環境が揃った時は、どの普通自動車よりも力強く走り、機能を最大限に活用して活躍する。
そんな車が、ギフテッドなのかなと思っています。
そして、そんな活躍できる季節、地域、環境に出合った時にようやく自分自身の存在価値を認められるのかもしれません。

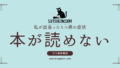
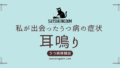
コメント