今回は、タロット占いを勉強していく中で出会った日本の和歌を用いた占い、「歌占(うたうら)」についてお話していきます。
歌占の起源
日本の室町時代の頃からあったとされるタロットカードですが、日本にもタロット占いに似た占いが古くからあったようです。
起源は、平安時代に神がかりの儀式で行われていたと言われています。
巫女(みこ)や男巫(おとこみこ)と呼ばれる霊能力を持つ人々が、神様が降りてきてその身に宿った状態(神がかり)で和歌を口にするのが、本来の歌占の形でした。この和歌が神様からのお告げであると考えられていました。
その和歌は、以前から存在していたものではなく、その場で神様から託宣(お告げ)として発せられた、新しい和歌だったようです。
これは平安時代の文献『十訓抄』に、神の心を表す和歌を巫女が人々に告げたという記録が残っています。この和歌は、神様からの直接のメッセージとして、その場限りで詠まれた特別なものとされていました。
変遷
これがタロットカードの起源とされているのと同じ、室町時代頃から形式を変えて普及し始めます。巫女が直接和歌を詠むのではなく、和歌を書いた札や短冊を引くようになりました。室町時代に作られた能の演目にも「歌占」があり、諸国を巡って和歌で占いを行う男が登場します。演目になるということは、当時の人々の間で歌占が広く知られていたのでしょう。
この頃は巫女が直接和歌を詠むわけではなく、それまでに詠まれた和歌が用いられました。それは特定の和歌集に限定されていたわけではなく、様々な和歌が使われていたと考えられています。
例えば、以下のようなものが推察されます。
歌占本で広まる
江戸時代になると歌占本が出版されるようになります。いつの時代も占いを扱う本は人気なのですね。その時に、鎌倉時代に成立した百人一首と結びついた「百人一首歌占鈔」という本が出版されています。その占い方はタロットカードに似ていて、
1.百人一首の札をすべて裏返しにして混ぜる。
2.占いたいこと(仕事、恋愛など)を心の中で念じる。
3.札を一枚引き、そこに書かれた和歌を読み解く。
という手順が示されています。和歌に込められた情景や心情を、自分の状況と照らし合わせて解釈することで、悩みに対するヒントを得るというものだったようです。
時代や場所が変わっても
時代も国も違うのに似たものが出来上がっていくというのは、不思議ですし興味深いですね。事柄の先を知りたい、真実を知りたいという気持ちは、いつの時代も同じなのですね。形式にこだわらなければ、古くは紀元前3000年~4000年頃の古代文明にも占いの記録はあるようです。
私はこの「歌占」をタロットの勉強中に始めて知りました。ただ、今でも多くの神社で引くことができるおみくじに和歌が添えられているのは、和歌が神の託宣であるという歌占の考え方の名残なのだとか。身近なところに昔からの文化は根付いているのだと知ると、感慨深いものを感じます。

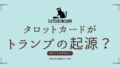
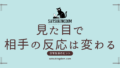
コメント