今回は、私がタロットカードを勉強していく中で出会った「タロットカードがトランプの起源である」という説についてお話していきます。
タロットカードとトランプの共通点
タロットカードは、大アルカナ22枚と小アルカナ56枚で構成されています。このうち、小アルカナ56枚がトランプの起源とされています。
スート(マーク)
小アルカナは以下の4つのスートに分かれています。
この4つのスートが、トランプのスートに対応していると考えられています。そしてそれぞれが中性ヨーロッパの社会階級や要素を象徴していると考えられています。
カードの構成
小アルカナの各スートは、1から10までの数札10枚と、ペイジ(Page)・ナイト(Knight)・クイーン(Queen)・キング(King)のコートカード(人物札)4枚、合計14枚で構成されています。
トランプはエース(1)から10までの数札10枚と、ジャック(Jack)・クイーン(Queen)・キング(King)の絵札3枚、合計13枚で構成されています。
この構成の違いは、トランプが小アルカナから派生する過程で、ナイト(Knight)のカードが失われたか、またはジャック(Jack)に統合されたため、と考えられています。また、ジョーカーは、タロットの「大アルカナ」にある「愚者(The Fool)」が起源であるという説もあるようです。
歴史的背景
タロットカードがいつ、どこで始まったかについては諸説ありますが、最も有力なのは15世紀前半のイタリア北部であるという説です。当初は占いのためではなく、貴族たちの間で楽しまれたゲーム用のカードだったと考えられています。大アルカナが切り札として使われる「トリックテイキングゲーム」という、タロットに近いカードゲームの存在が記録に残っています。
このゲームがヨーロッパ各地に広まり、特にフランスで庶民の間で広く普及していく中で、よりシンプルで持ち運びやすい遊戯用カードとして変化していきます。その過程で「小アルカナ」の部分が独立し、それが現代のトランプへと進化した、という流れが考えられています。
今は占いの道具として使われているタロットが、最初はゲームの道具だったとは、不思議なものですね。手軽さはトランプに、崇高さはタロットに分化していったようなイメージでしょうか。
諸説あります
世の中の歴史には諸説あることが通例です。
構成やスートの共通点から、かなり説得力がある説だと私は思っています。ただ、タロットの起源そのものにも諸説あるようで、この説も絶対的な事実として証明されたものではないようです。数百年前のことですし。日本では室町時代の頃ですね。トランプの方が先にあって、タロットはそこに大アルカナという特殊な絵札を加えて複雑にしたものだという、全く逆の説もあるようです。
確かに、小学生の頃にトランプを使った占いをする友達がいたような記憶もあります。トランプを占いに使い始めた結果、占いに便利な特殊な絵札が増えていったというパターンもあるのかもしれません。
私は、タロットカードが遊戯用として貴族の間で楽しまれ、その後簡略化されたカードが庶民に普及していったものがトランプだという流れの方が自然な気がするので、そちらに一票。
ここでは、「小アルカナがトランプの起源」らしいよっという結論を出しておきますが、歴史は確定しないからこそロマンがあるものなのかもしれません。室町時代からあるタロットってすごいですね。日本でいう百人一首(1235年頃)に近い存在を、現役で占いに使用しているんですね。
余談ですが、百人一首を用いた占い「歌占(うたうら)」が神社のおみくじのに和歌が書かれている起源だとか。あ、諸説あります。

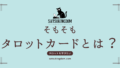
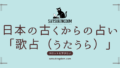
コメント