今年の夏も暑いですね。夏に蝉が鳴いているのを聴くと、毎年思うことがあります。
今回は、そんな私の話を聞いてください。蝉に対するイメージが変わるかもしれません。
蝉の一生は短い
皆さんもご存知の通り、蝉は地上に出てきて1週間程度の命しかないと言われますよね。何年も土の中にいて、少しの間しか生きられないので儚さの象徴として扱われることもあります。
角田光代さんの小説でも『八日目の蝉』というタイトルがあります。もし八日目まで生き延びる常識や社会ルールから外れる蝉がいたとしたら、その蝉は他のどの蝉も見たことのない景色を見ることができる、という比喩的な意味が込められています。作中とリンクする部分の多いインパクトのあるタイトルは、蝉が「七日で死ぬ」という通説が広く定着した理由の一つかもしれません。
実際のところ、蝉の種類にもよりますが土の中で2年から長い種類だと17年過ごします。土の中で、木の根から樹液を吸って成長していきます。そして何度も脱皮を繰り返して過ごしています。そんなに長く土の中にいて、地上に出てからは長い種類でもたった1カ月程度で一生を終えてしまうのです。儚いですね。
違和感はありませんか?
ここまで読んで、違和感はありませんか?私は毎年納得がいきません。「蝉=短い一生」というイメージが定着していますが、十数年生きている種類もいます。少なくとも数年は生きています。
確かに「地上に出てからは短いんだから、間違いではない」ということは理解できます。ですが、それは人間が勝手に「蝉の一生のメインは地上に出てから」と決めたからですよね?蝉たちにとっては、地上の期間はただの「老後」なのかもしれません。私たち人間でいう青春や壮年期の楽しみは地中にあって、地中こそがわが人生。蝉としては地上には出たくない。ずっと地中に居たい。
そんな可能性はないのかな?といつも思ってしまいます。蝉がよたよたと這い出して静かにしていれば、もしかしたら蝉の一生のイメージも変わっていたかもしれません。地中から出てきてしまって、可哀そうにって。
短い一生、儚い一生というならば蝉ではなく蚊であるべきです。卵から数日でかえり、ボウフラとして一週間程度過ごし、数日のサナギ期間を経て成虫になります。成虫で生きる期間は、オスは数日、メスは2週間から1か月です。蝉の地上期間が、蚊の一生と同等です。しかも、人間はあの手この手で命を狙ってきます。寿命を全うできる蚊は限られます。まあ可哀そう。
こんなに漢字が似ていて紛らわしいのに、扱いのどれほど違うことか。
はい、屁理屈を言いました
すべてはイメージのお話ですよね。
蝉があれだけ騒いでいるのだから、地上に出てきて嬉しいのだろう。暗くて冷たい地中から出てきて、明るい日差しを浴びながら大空を飛んでいる。それは素晴らしいことに違いない。でもそんな素晴らしい期間がたった1週間程で終わってしまうのはなんと儚いことか。わかります。
そして、ブンブンと人の周りを飛び回って。次から次へと出てくる。払っても払っても血を吸いに来てしぶとい奴め!どれだけ対策をしていても窓を閉めていても、どこから入ってくるんだまったく。
これでは、イメージで蚊が敵うはずはありません。蚊も一生懸命、子どもたちのための栄養を確保するために、危険を顧みず血を吸いに来ているんですけどね。一生のうちに3回から5回しか血を吸わないと言われています。オスは子孫を残す行動をとれば数日の命ですし。
イメージって怖いですね。
このイメージはいつから?
「蝉の一生は儚い」というイメージは、古くは万葉集にもあります。「空蝉(うつせみ)」という蝉の抜け殻を表す言葉を使って、世の中の儚さを詠ったものがあります。
「うつせみの 世は常なしと 知るものを 秋風寒み 偲ひつるかも」
大伴家持
【この世は永遠ではないと知っているのに、秋風が寒々と吹くので、しみじみと物思いにふけることだよ】
『万葉集』の巻3に収められており、亡くなった妻を偲んで詠んだ歌とされています。この時代から、儚さの象徴の片鱗が見えます。ここでは抜け殻のように人の肉体は、この世での仮の姿であって儚いという意味なので、蝉の一生とは少し異なりますが。
そして、「蝉の一生は7日間」というイメージについては、江戸時代からあったと言われています。(※諸説あります※)蝉を捕まえて虫かごで飼育した時に、すぐに死んでしまうことが多かったからだと言われています。蝉が樹液を吸うための環境を再現するのが難しいため、長期飼育は難しいようです。皆さんの中にも、小学校の頃捕まえた蝉がすぐに死んでしまって「蝉の一生って短いな」と思った経験をした方もいらっしゃるのではないでしょうか。ちなみに私は今でも蝉に触ることすらできないので、友達から聞いた記憶しかありません。
イメージは大事
こんなに古くからあるイメージに私が疑問を持って抵抗したところで、そうそう変えられるわけもありませんね。それだけイメージって大事で、良くも悪くも影響されるということです。事実がはっきり判明した後でも、古くからの思い込みの方が勝ってしまうのですから。
日常、いろんなイメージに振り回されている世の中です。身の回りの人や事柄を、勝手なイメージで判断してしまわないように気を付けたいものです。
この思いは、毎年蝉の声を聴く度に思い出されます。

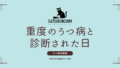
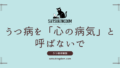
コメント